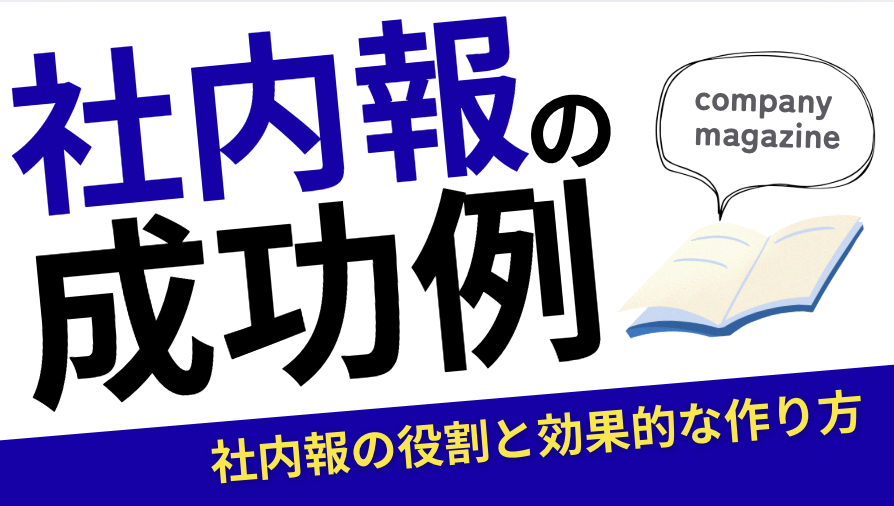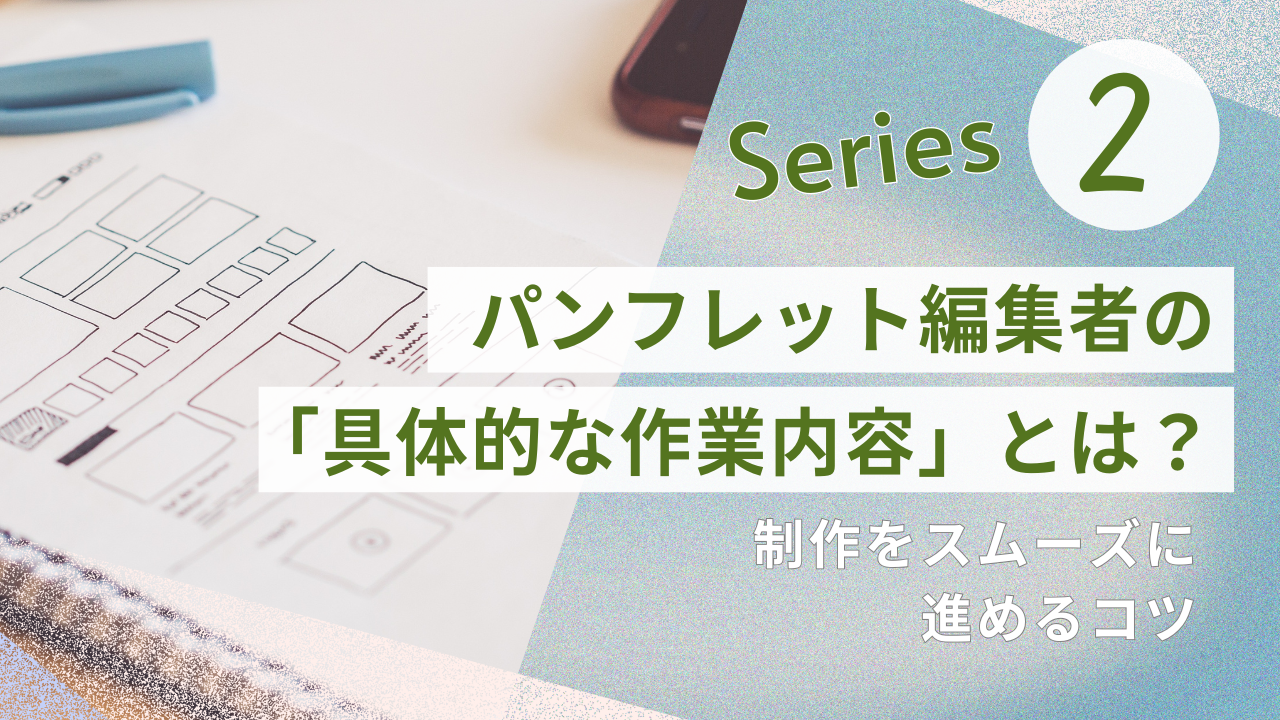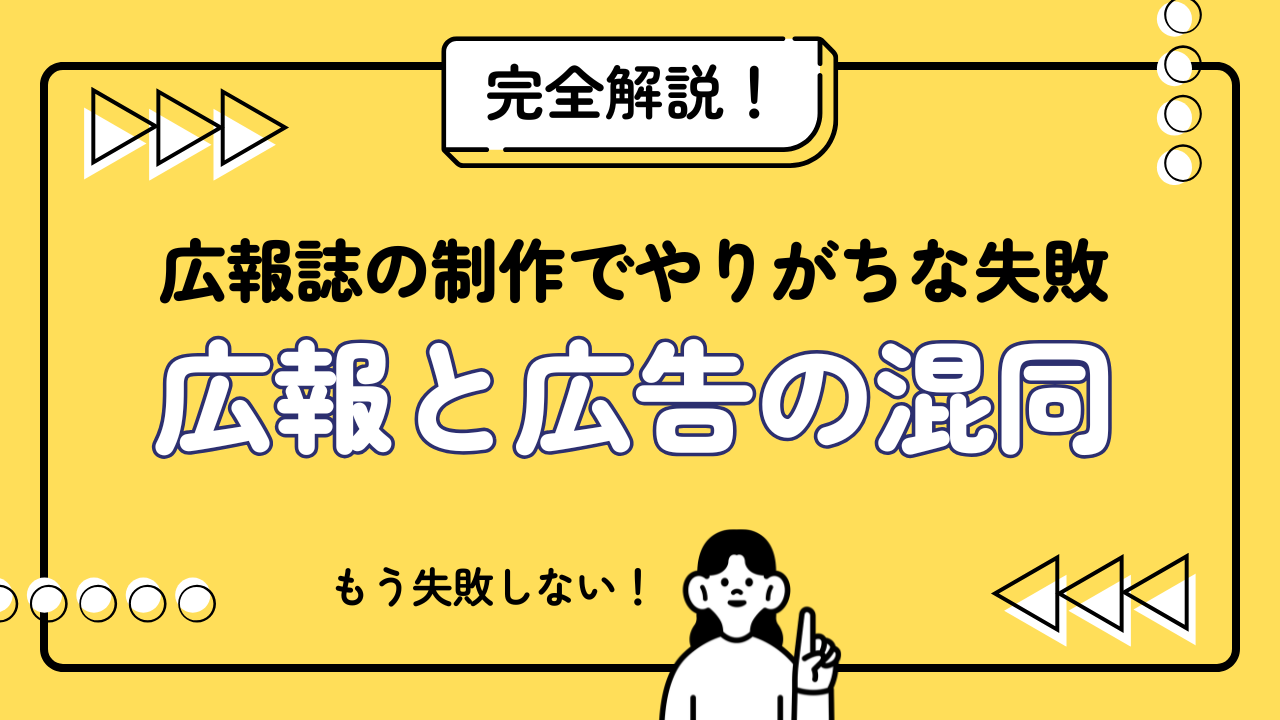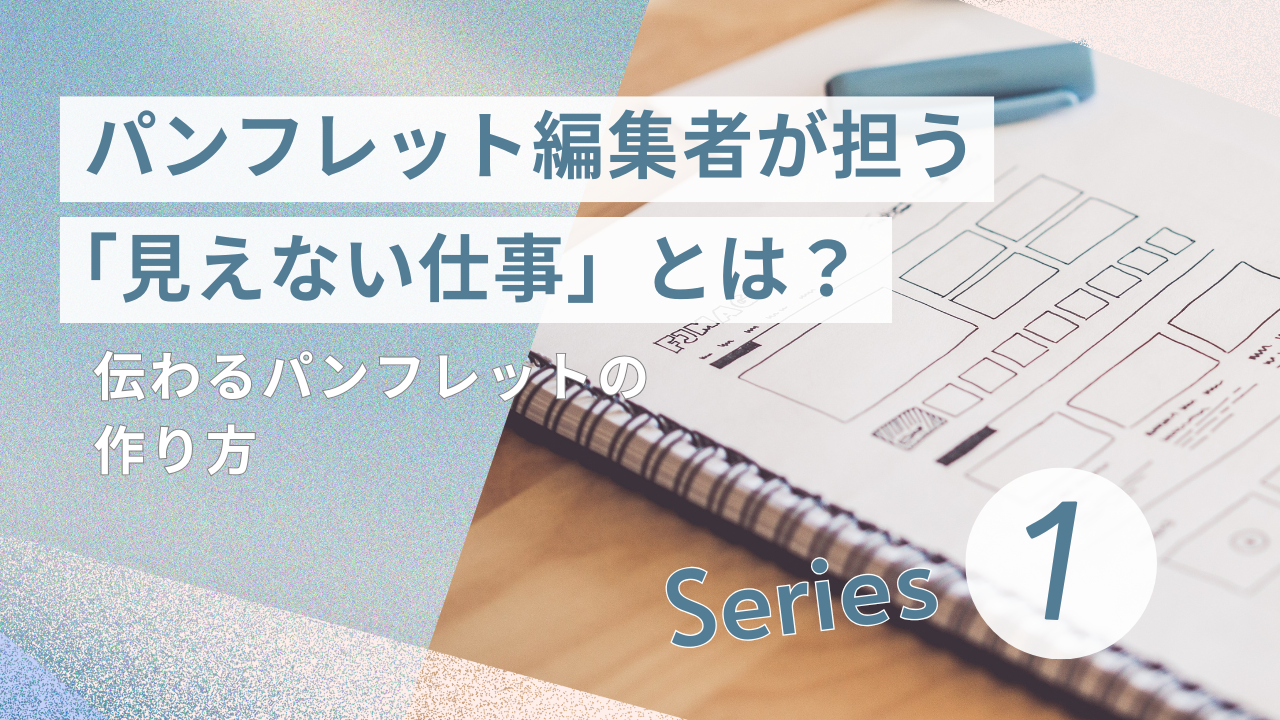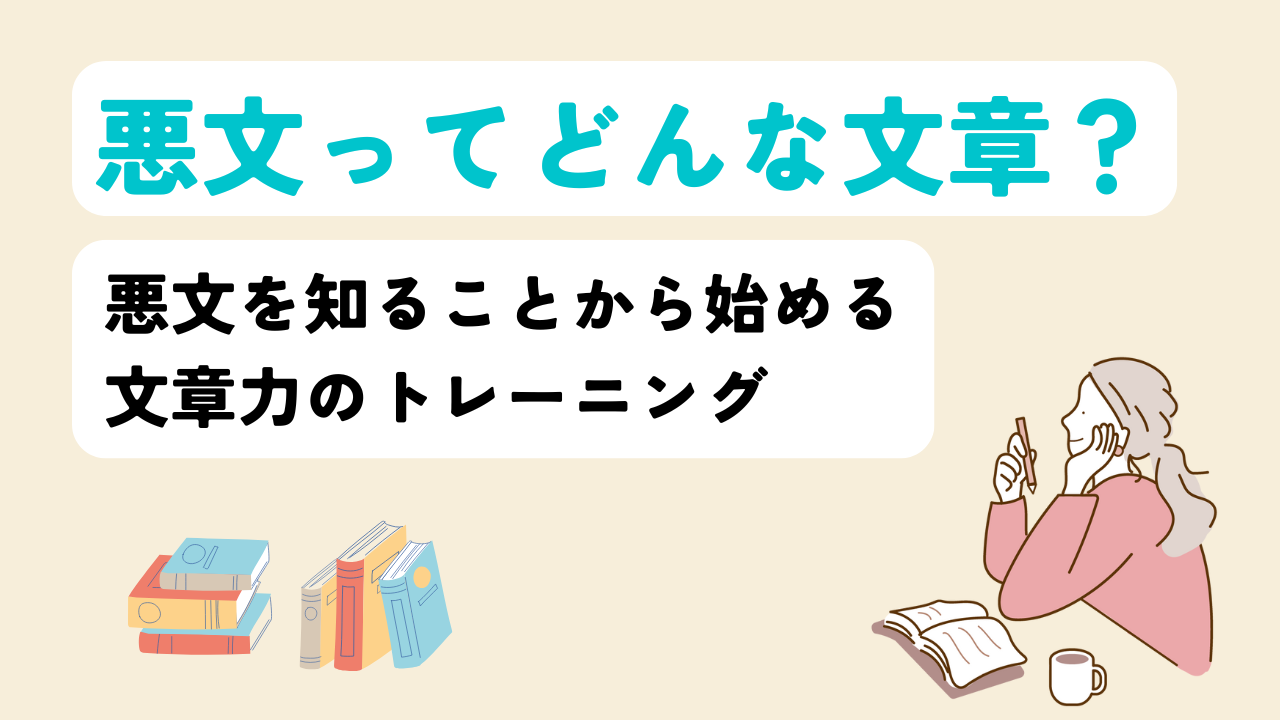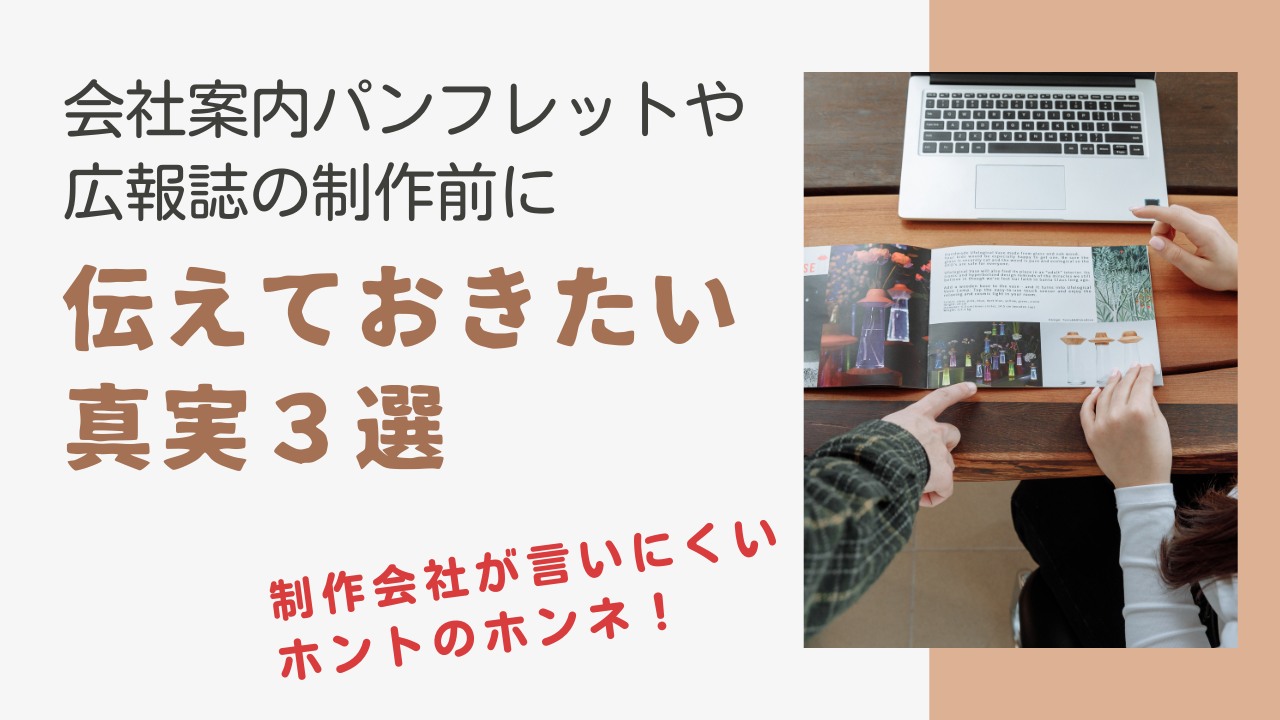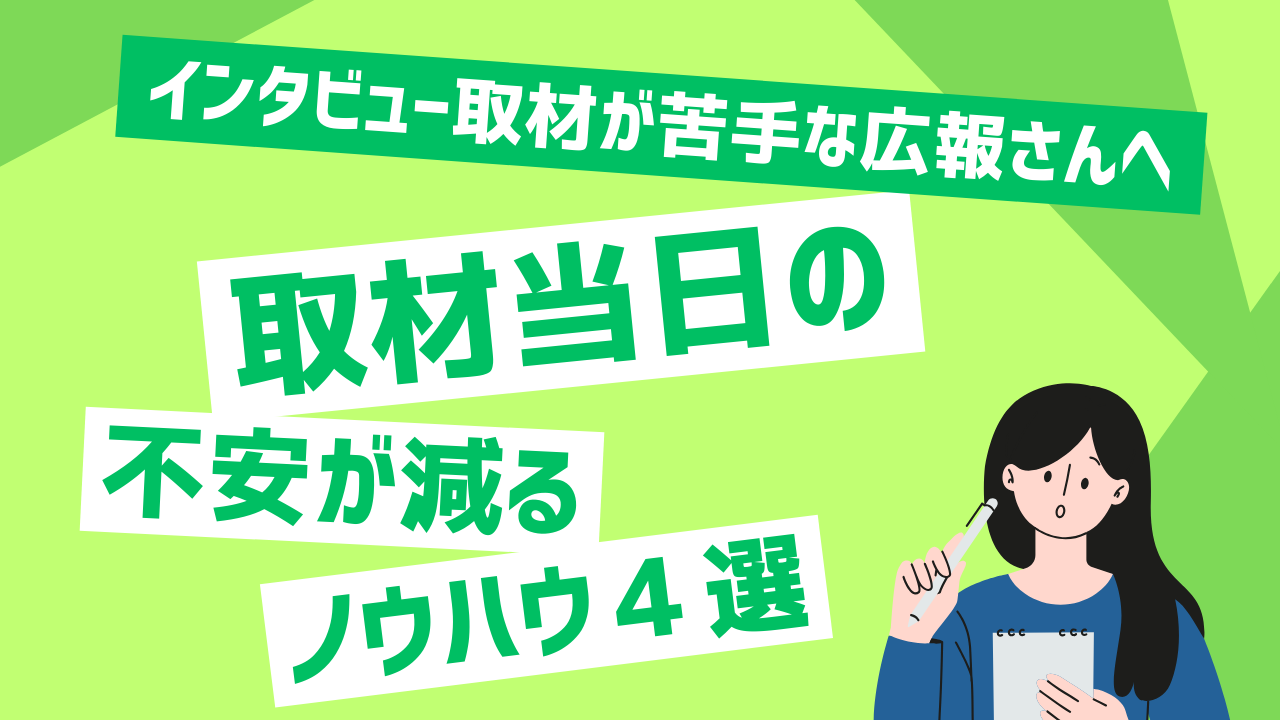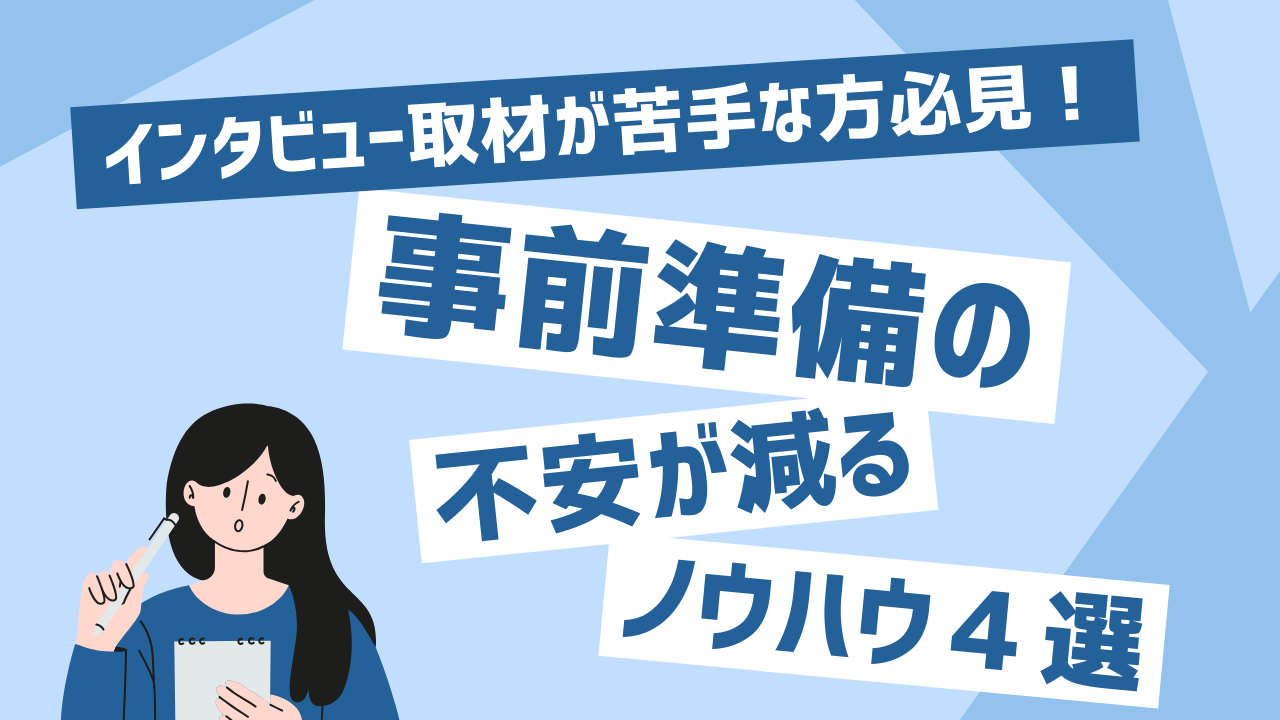社内報の制作は「めんどう」「つまらない」?
「担当を外れたい…」
「作るのがしんどいです…」
これまで、複数の社内報の担当者の方からこうしたセリフを耳にしてきました。確かに、社内報のような定期刊行物を担当すると、身も心も疲れ切ってしまうんですよね…。
とはいえ、社内報制作は本来、クリエイティブで楽しい部分も多い仕事のはず。そして、まずは作り手自身が楽しむことが「読まれる」社内報の第一歩。
そこで、社内報の制作はなぜそんなにしんどいのか、という分析に加え、社内報作りを楽しく、効果的に進めている会社さんの実例をご紹介することで、しんどさを解消するポイントをご紹介したいと思います。
社内報の制作が「しんどい」理由
まず、社内報は広報誌や記念誌といった冊子類と同じく、「オーダーメイド品」です。だから、どうしても作るのに手間がかかります。
それを前提とした上で、社内報ならではの難しさ、しんどさはどんなところにあるのか挙げてみました。
社内報は効果を「実感」しにくい
社内報の目的は、一般的に以下に挙げた4つの「-tion」に分けられるとされています。
・コミュニケーション(Communication):社内交流の促進
・インフォメーション(Information):社内情報の伝達、共有
・エディケーション(Education):理念・ビジョンの浸透、社風形成
・モチベーション(Motivation):主体性・やりがいの向上
この4つの目的、どれも言葉としては「その通りだよね」とは思うものの、いずれの目的も達成を実感することが少々、難しい気もします。
「いやー、最近は社内報のおかげで、ビジョンの浸透が進んできたねー」
「社内報を出してから、社員の主体性が上がってきたなあ」
とか、あんまりならないんじゃないかなあと。
さらに、これらの目的に加えて、ネットで調べてみると、
・自社製品やサービスへの愛着の形成
・会社へのエンゲージメントの向上
・インナーブランディングの促進
といった、実にさまざまな言葉で社内報の目的が説明されています。が……ぶっちゃけ、ここまでくると、そもそも言葉として分かりにくい気がします。
このように、自分は何のために社内報を作っているのか?本当に役に立っているのか?目的や効果が見えにくい媒体であることが、しんどさの原因のひとつになっているのではないでしょうか。
社内報担当者は「孤立」しやすい
これまで私が関わってきたほとんどの社内報は、担当者がおひとりでした。
ひとりで冊子を作るなんて、絶対に大変です。
加えて、その大変さを理解してくれる人が周囲にいない。それもしんどいと思います。苦しさを共有したり、グチを言い合ったりできないってつらいですからね。
そして、社内報の担当者さんは、各部署に記事の依頼をしないといけません。これがまた、結構、嫌がられると聞きます。そりゃあ皆さん忙しいでしょうから、記事の依頼がきたら面倒くさがるでしょうし、後回しにもしてしまうでしょう。
でも、制作側としては切実な問題です。締め切りに間に合わせることも大切な業務ですから、「まだですかー」「早く出してくださいー」と催促せざるをえません。
こうしてさらに周囲から面倒くさがられていく……完全に負のループですね。
その結果、「良い社内報を作る」から「とりあえず社内報を作る」という意識へ変わっていき、本来、楽しい部分もあるクリエイティブな作業が、ただの事務作業になっていくのです。
そうしたマインドで作られた冊子が、読者を楽しませることは稀だと思います。
社内報が「読まれない」こともしんどさの要因に
それでもまだ、「社内報読んだよ」「新企画、面白かった」などのリアクションがあれば、モチベーションを保てるかもしれません。
ただ、周囲からそういったリアクションがよくあると話されていた担当者さんは正直、レアです。むしろ「だーれも読んでくれてません…」と、肩を落とす担当者さんの方が多数でした。
社内報の「読まれない問題」も、目的が分かりにくい問題と同じで、作る側のやる気をくじくには十分です。
というわけで、じゃあどうしたらこれらの「目的が分かりづらい問題」「孤立しがち問題」「読まれない問題」を解消できるのか?
ここからは、私の回答として、理想的ともいえるある企業の社内報制作の実例をご紹介したいと思います。
社内報の制作体制の理想的な実例
これは私が制作に関わった、とあるメーカー・A社さんの社内報制作の実例です。
A社さんも、それまで社内報を出してはいたものの、あまり読まれていなかったそうです。
それが、社長さんが代替わりしたことをきっかけに、「せっかく作るのなら、読まれる、そして効果のある社内報にしよう」ということで、ガラッと制作体制を変えられたのです。
その体制が本当に合理的かつ理想的で、先述した社内報担当者が抱えがちなさまざまな問題を解消できていたので、ご紹介します。
社内報の制作は「若手社員」が担当
まずその会社では、社内報の制作は若手社員に任されていました。
それ自体は珍しくはありません。社内報を担当すると各部署のことや会社全体のことが分かるため、新人教育に最適だからです。
ただ、A社さんの方法が秀逸なのは、ひとりふたりの若手に任せるのではなく、各部署から1名ずつ若手を集め、7〜8名の編集委員会を設けた点にあります。
これなら孤立はしません。いっぱい仲間がいますから。
そして、年齢も社歴も近い若い方同士、編集会議はいつもワイワイガヤガヤと、良い意味でにぎやかな雰囲気の中、進められていました。
アイデア面でも流行りや旬をうまく取り入れた企画案が頻繁に出され、ユニークな誌面企画につながっていたのです。
ひとりでウンウンと悩んで生み出す作り方とは、大きく異なります。
社内報を「楽しみながら」制作する
といっても、集められた若手の方々は誰ひとり広報経験者ではありません。
にもかかわらず、なぜ面白い企画を生み出すことができたのか?それはひとえに「楽しんでいたから」だと思います。
この体制を考えた社長さんは「とにかく若手に自由にやらせよう」と方向性を決められました。そして、ご自身は「口は出さない」と明言されていました。
ただ、実は広報担当者さんはいるんです。
社内報のほか、さまざまなパンフレットの制作経験がある方がちゃんといるのですが、その方も編集会議では司会進行に徹していました。
特に「それはおかしい」とか「そんなのやめた方が」などといったネガティブな言葉は口にされませんでした。若手が困っていたり、アドバイスを求めてきた時だけ、知っている知識を伝えるなど、陰のサポート役に徹していたのです。
これも、社内報作りのさまざまな負担を軽減する、うまいやり方だと思うと同時に、この広報担当者さんもご自身の役割を理解された、非常に優秀な方だと感じました。
そうした安心できる環境の中、冊子づくりが初めての若手の社員さんは、時には助けを借りながら、でも基本的には自由に誌面の企画を考えたり、記事を依頼する社員さんを探したりしていました。
実際、出来上がった誌面は私が関わった社内報の中でもダントツでポップで、はじけていて、とにかく「楽しい」雰囲気に満ちていました。
人気バラエティ番組をもじったトーク企画や、人気ファッション雑誌のような私服紹介企画など、「社内報とはこういうもの」という固定観念がない分、プロの私からは出てこないような斬新な企画が満載でした。
社内報なので、実際の誌面をお見せできないのが本当に残念です。
やはり、作り手が楽しんでいれば、明らかに誌面にもその空気感が反映されるのだと改めて実感しました。
制作を担当する若手は「交代制」
さらに「よくできているな」と感心したポイントがあります。
それは、各部署から集められた若手編集担当者が1〜2年で数名ずつ交代していくという方式です。
つまり、ほぼ毎年、少しずつメンバーが入れ変わっていくのです。なので、たとえ新人として編集委員に入ったとしても、もうすでに1〜2年経験している先輩が5〜6名いるわけです。
これも、非常に心強いですよね。
実際、すでに何冊か制作している「先輩編集者」が会議を引っ張ってくれるため、「何から始めればいいの?」「企画が思いつかない…」といった悩みを抱えている方は見かけませんでした。
つまり、社内報担当者の教育システムが自然とでき上がっているのです。
とはいえ、何年も続けていると、いくら楽しくても勤続疲労は出てくるもの。
その点も、この交代制によって解消されています。だいたい3〜4年で、編集委員から外れるわけですから。
最初メンバー入りした時は「できるかな」などと不安を抱えていた社員さんも、メンバーを外れる際には「もっと関わりたかった」「もうちょっとやってもいいかも」などと、よくおっしゃっていたことを覚えています。
社内報への「協力体制」の醸成につながっている
さらに、この交代制のおかげで、必然的に1〜2年ごとに各部署の誰かが社内報担当を兼任することになります。
これも大きなメリットなのです。
ひとり広報さんの場合、その苦しみを誰にも分かってもらえない「孤立しがち問題」について先述しました。それが、このシステムだと、社内報制作の苦しみや楽しさを理解できる社員が、毎年、各部署にどんどん誕生していくわけです。
それは同時に、各部署への記事の依頼など、協力の要請がしやすくなることを意味しています。
なぜなら、一度でも制作側を経験すれば、協力の依頼の難しさを痛感しますから、メンバーを外れてからも記事を依頼されれば、「協力しよう」という意識を持ってくれます。
こうして「記事をお願いしにくい問題」や、そこから派生する「依頼した記事が返ってこない問題」や「記事の回収に時間がかかる問題」も解消されるなど、社内報の制作に協力的な社風ができ上がっていくのです。
むしろ、すでに制作を経験した社員さんからすると、自分の「後輩」たちが、新たにどんな企画を立て、どんな誌面を作るのか興味津々という感じでした。
社内報制作委員会から毎年、数名の卒業生が自部署に戻っていくたびに、この社風は強化されていくのです。やっぱり、自分がかつて作る側だったから気になるのでしょう。
これも、制作していた時に「楽しかった」ことが大きいと思うのです。楽しかったからこそ気になるし、協力したい、という気持ちになるのではないでしょうか。
そして、そんな楽しい誌面が毎号届けられるため、発刊当初は登場を断られることも多かったのですが、徐々に「こういう誌面なら」と、協力してくれる方が増えていきました。
数号発刊されて時点では、自分が載ることを厭わない社員さんがかなり増え、結果、毎号多くの社員さんの顔が載るにぎやかな社内報になっていきました。
社内報に「巻き込む」ことでしんどさは変わる
以上が、実際に私が関わった理想的な社内報作りの全貌です。
ここまで読まれてきて「理想的なのは分かるが、うちでは無理」「非現実的」といった感想を持たれた方も多いでしょう。
確かに、いきなりこの会社の通りに体制を変えて、各部署から新人を集めることは簡単ではないと思います。
ただ、ポイントはあります。それは、多くの人を「巻き込む」ことです。
といっても、作る側に巻き込むのではありません。もちろん、各部署から人を集めた体制が組めれば素晴らしいですが、すぐには難しいですよね。
であれば、その前に「載る側」として巻き込むのです。
時々、社員が誰も登場せず、社長さんやお偉いさんからのメッセージや、各部署からのお願い・注意事項しか載っていない社内報を見かけます。
本当にもったいないです。
どんどん人を載せましょう。いろんな部署を、いろんな人の顔と声をです。そうすれば、どんどん「読まれる」社内報になっていきます。
なぜなら、人は自分自身、あるいは知り合いが載っている誌面には興味を示すからです。そうすることで、多くの社員さんにとって社内報を「自分ごと」にしてもらうのです。
自分ごとではないから読まれないし、協力も後回しにされてしまうのです。
多くの社員さんを巻き込んだ誌面に変えていくだけでも、社内報の注目度が変わっていき、理解を示したり、協力してくれる社員さんも増えていくはずです。
社内報の役割は「働きやすさの改善」
冒頭で、社内報の役割は実感しにくいものが多いとお伝えしました。
4つの「-tion」はともかく、エンゲージメントとかインナーブランディングとかいわれると…。正直、私はさらに分かりにくくなっているように感じます。
そんな私は、これまで社内報の目的・役割は、「平たくいえば、働きやすさの改善です」とお伝えしてきました。
A社の例などは分かりやすいですよね。あえて4つの「-tion」でいえば、「Communication」の面で、働きやすさが改善されているといえます。
具体的には、以下のように。
【他部署とのコミュニケーションの強化】
・編集委員会で、業務で関わらない部署の方との接点が生まれる。
・編集会議で、色々な部署の情報を知ることができる。
・数年ごとに新人が入るので、若手のつながりが広がっていく。
【自部署内でのコミュニケーションの強化】
・自部署の社内報経験者にアドバイスを求めたり、「今こんな企画してるんです」といった会話から、社内報経験者同士のつながりが生まれる。
【個々の社員とのコミュニケーションの強化】
・記事の依頼などを通じて、接点のなかった社員さんとのつながりができる。
・毎号、多くの社員さんに依頼するので、数年担当するとかなりの部署や社員さんと関わりができる。
・誌面に多くの社員さんが登場し、仕事内容や考え方、プライベートについても発信しているため、いち読者としても他部署や社員さんについて知ることができ、会話のきっかけになる。
4つの「-tion」は効果が分かりにくいとはいえ、ここまで効果がハッキリしていれば、さすがに実感できます。
そして、このように部署内はもちろん、部署の垣根を超えた社内人脈が広がっていくことは、仕事面でも精神面でもプラスになるはずです。
特に、若手社員にとって知り合いが増えることは、大げさにいえば「味方」が増えるということでもあると思います。
A社の社内報は、少なくとも「若手社員の働きやすさ」を向上させていると、私は感じていますが、皆さんはいかがでしょうか。
もし今、社内報の制作で方向性や目的が見えずに困っていたら、できるだけ人を巻き込むとともに、「働きやすさの改善」という視点で企画や人選、文章などを捉え直してみてください。
ご自身の社内報制作の進めやすさはもちろん、誌面の掲載内容も良い方向に変わっていくと思いますよ!
社内報の制作に関するご質問・ご依頼は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。編集者がしっかりと効果の出る社内報の制作をゼロからサポートいたします!
⚫︎初回40分無料のオンライン制作相談も承っております!
⚫︎eパンフLabトップページ